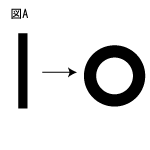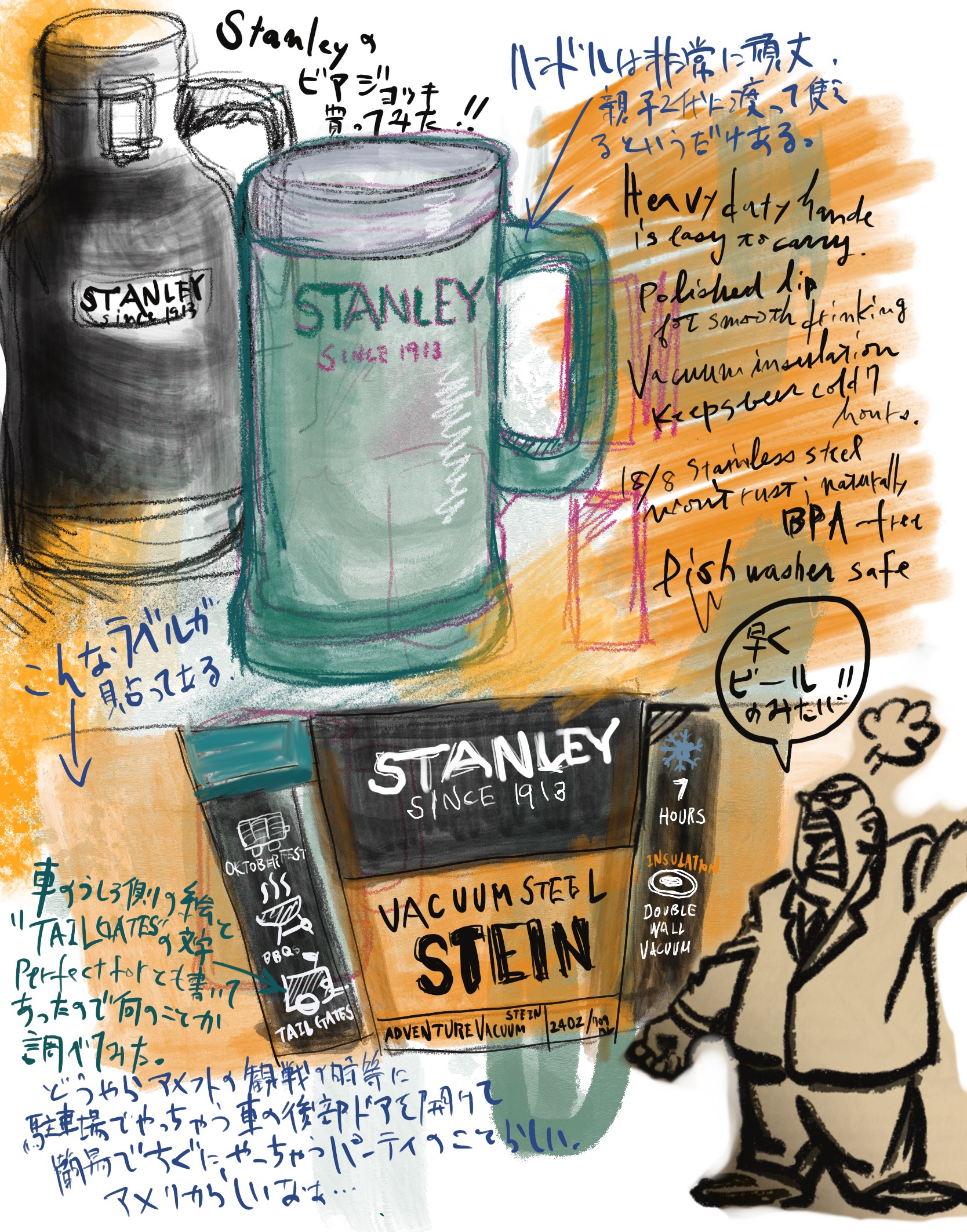blank blanq bianco
最近荒地に放置された埃まみれのガラスのショーケースを見た。
札幌オーロラタウンから一本それた地下街の通りに、広告のオブジェをいれる大きなガラスに包まれた箱状のアドスペースがあるんだけど、小さいころにを母親に連れられて歩くたびに、あれを見るのがイヤだった。なぜかというと、ガラスの中の物体が時間から取り残されているような感覚に陥るから。
大人になってからは、クリストのパッケージとか、アルマンのアキュミュレーションとか、ジョージ・シーガルの彫刻を見ては同じような気分に陥いった。冷蔵庫の中に取り残された賞味期限切れのチューブワサビを見てもあまり同じような感覚にはならない。ジョージ・シーガルの彫刻が人間であることをやめてしまった様に見えるのと同じで、アドスペースの中の空虚なトルソー達は、トルソーであることをやめてしまったように見えた。
最近荒地に放置された埃まみれのガラスのショーケースを見て突然その感覚を思い出した。しばらく、呆然と眺め、その中に本来あるはずだったケーキのことを考えて立ち尽くした。ショーケースはなにか空白を詰め込んで「ただそこにあった」。空白について思いをめぐらすのはドーナツの空白のこと程度だと思っていた。ドーナツの内径がドーナツの直径と重なる時ドーナツは消失する。
遠くに響く笛や太鼓。お祭りを遠くから見る感じは、どこか自分が取り残されたような感じがする。時間から取り残された荒地のショーケースのような空白の部分が自分の中にあるのだと思う。だからこそ怖いのだ。
「あなたを思う。
それは子供の頃、窓の外に見ていた風景で
額縁の中の絵で、陰鬱でない青で。
ただ私は、その何処か片隅に潜って
眠り込みたいだけなのです。」
数年前に行方のわからなくなった友人の女の子から、海辺で拾ったと思われる穴が開いた石と共に僕宛にある日一通の手紙が届いた。
石の穴を覗くたびに、僕はそのたった5行の文章を何度も反芻して自分の空白について考えた。
「あなたは多分、空洞のようなもので出来ているのだと思う。だからシャベルで土を積み上げて山を作った結果、積みあがった山よりもぽっかりとあいた空白に興味を持つのでしょうね。」
果てしなく続く雨のようにペーパーカップの中へ空白が満たされていった。