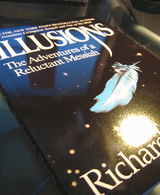失ったMoleskineを手に入れるまでの考察 #6

前回の続き:僕のMoleskineを発見したBとの対話。小樽のカフェで会って受け取る約束をした。
僕らは、灯台の近くの海に面したそのカフェで会うことを約束し電話を切った。
結局、そのお店で、Bは勤務をしているのか、それとも訪れるのかがわからない状態で漠然としたまま電話は終了した。電話が終わった後も僕はぼんやりしていたが、時間が経過するにつれてそれは薄れていった。雲自身が空をこの方向に動いていくのを知らないように、僕自身も知らないことがきっと多いのだ。
—
モレスキンの空白のページを眺めたときに、僕らは心の中にも空白のページを持っていることに気づくことができる。
その殆どはきれいに書きとめることができず、ぐしゃぐしゃとした筆跡で「計算」がただ書き込まれていく。しかし、もちろん僕らが望むならば、そこにはただぼんやりと考えた意味のないことを書き留めたり、美しいと感じた写真やスクラップを貼り付けたり、自分のお気に入りのささやかなページを追加することができる。そういったモレスキンに愛着が沸くのと同じように、後で眺めても楽しめるフェバリットなページを心に増やすと、愛着のある自分になっていくのかもしれない。
モレスキンを引き取りに行くまでの数日間、最初はカバンの中にいつもの黒いノートが無いのを見るたびになんとなく空虚な気分がしていたが、「モレスキンを迎えに行く」というささやかな物事が、自分自身の心を暖かく変化させているような感じがしていた。
—
遠くの山々は、黄色のカーペットを少しずつ敷き詰めるように紅葉を開始していた。近所の公園の広葉樹の下の枯葉が少しずつ積もっていく。子供たちが大きな枯葉を持って走り去っていく。遠くの遥か上空でヘリコプターが乾いた静かな音を立てていた。
10月に入り、モレスキンを引き取りに行く当日。その日は秋にしては少し暖かな日であった。
少々早い時間ではあったが、向こうで時間をつぶすことを考え、早めに札幌を出発することにした。
何か音楽が欲しかったが、なんとなく車の窓を少し開け、ただエンジンが吹け上がる時の乾燥した鼓動と風の音を聞いていた。ゆるやかな風が上着の内側に入り込んできて汗を少しかく。
無機質な高速道路に入り、僕は移動する。右側には海岸が見えてくる。高校時代に服を着たまま皆で飛び込んで遊んだ海だ。
運転をしながら僕は、Bが伝えてきたカフェの名前は、その昔付き合っていた彼女と入った店と同じであるという偶然についてぼんやりと考えていた。広い街ではないため、そういった小さな偶然も起こりえるのかもしれない。
当たり前だが、昔の彼女に対しての未練と言ったものはない。ただ、「無くしたモレスキンを再び手に入れること」と「過去の時間と今の時間がリンクすること」が、何か似ているように感じた。
無くしたモレスキンを手に入れる旅は、何か別なものを手に入れる旅なのかもしれないと思った。
この小さな偶然は、単なる一致であっても構わないのだが、ただその当時の、若いが故にうまく消化できない切ない感覚を思い出してしまい、少しつらくなった。
気を紛らわすために高速道路の壁面に打ちつけられた「薄いグリーンの金属板」の、場所を表す数字なのかわからないが、とにかくそれを数えた。一つくらいは自分の誕生日と同じものがあるのかもしれない。いったいこの数字はどこまで続くのだろう?数えているうちに、なんとなく、限りなく遠くに向かっている気分に陥った。
昔、彼女と一緒に出かけた美術館の展示で、「高速道路の模型のようなオブジェ」を見たことがあるのを思い出した。それは、道路の部分がメビウスの輪のようにただ交差しているオブジェで、パッと見は高速道路をイメージした小さなコンクリートの模型のように見えた。表面は真っ白なペンキで全体をくまなく塗られている。そして何度もループするその道路には出口がどこにも無かった。
もし、そこを車で走るなら何回もバイパスを通り抜け、無機的な薄いグリーンの金属板に書かれた数字をえんえんと僕達は目で追い続けなくてはならない。その彫刻を眺めているうちに、不自然な感覚を味わったのを覚えている。出口のない感覚というのは極めて人を不快にさせる。僕らは美術館の中で、そのオブジェを、初めてライターの火を見たアラスカの動物みたいに一緒にぼんやりと眺めた。
「ここを走る車たちはどこに帰るのかな?」
「入り口も出口もないからガソリンが切れるまで車は走るんでしょうね。その後は歩き・・・、水を求めて歩きだす・・・、きっとオアシスは遠いわ。」
「まるで<世界の果て>みたいだ」
対抗車線はほとんど車は走っていなかった。
と思うと前方からすさまじい程のスピードを上げた1台の車が、風を切り裂いていく。僕はそんな古い会話を思い出しながら、ただ風のびゅうびゅうと鳴る音を聞いていた。
センチメンタリズムは、一滴の雨のように突然僕らの頭の上に落ちてくる。それは、誰にも防ぐことはできない。あなたがどんなに幸せの中にいたとしても、その一滴はじわりと侵食していくのである。